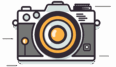ユニクロの柳井正会長が最も恐れる「大企業病」。組織の硬直化と過去の成功体験への執着が変革を阻む現象だ。これを熟知している柳井氏は、組織を「揺さぶり続ける」ことで変革を維持しているという。たとえば、執行役員の評価は従来の常識とはかけ離れたものになっているという。こうした背景にある柳井氏の強烈な“信念”とは何か。『ユニクロの戦略』を上梓した、元ファーストリテイリング執行役員でUNLOCK POTENTIAL/リード・ザ・ジブンCEOの宇佐美潤祐氏が、柳井流「大企業病撲滅作戦」の全貌を明かす。

ユニクロはいかにして「大企業病」を回避しているのか?
(Photo:VTT Studio / Shutterstock.com)
典型的な「大企業病」──コダックの“悲劇的”末路
柳井さんは、企業を経営する上で「大企業病」を最も恐れています。大企業病とは、企業が成長し大きくなるにつれて、組織が硬直化し、過去の成功体験に縛られて、イノベーションが起きなくなる現象を指します。「今のオペレーションをいかに効率良くするか」という現状維持に重きが置かれ、変革が行われなくなるのです。
これは「服を変え、常識を変え、世界を変えていく」というパーパスと真逆の状態です。パーパスが示す「変革」という方向性と、大企業病がもたらす「現状維持」や「わずかな改善」という方向性は相容れません。
そのため、ユニクロでは組織を常に「揺さぶり続ける」ことで、大企業病を避けようとしています。組織や人事の固定化を避け、常に変化し続けることを重視しているのです。
大企業病を避けるためには、常に変革を続けることが必要です。同じことをずっと続けていては、企業は成長を続けることができません。過去にうまくいったからと同じことをやり続けていても、環境が変わってしまったら通用しなくなり、誰にも見向きもされなくなることは珍しくありません。
この「大企業病」の典型的な例として、写真フィルム業界の盟主だったコダック(イーストマン・コダック社)の凋落が挙げられます。1880年代に設立されたコダックは、長らく写真フィルム市場で80%以上のシェアを持ち、「コダック・モーメント」という言葉が生まれるほど、写真文化そのものを象徴する企業でした。
しかし、1990年代後半から2000年代にかけてのデジタルカメラの普及、さらに2010年代のスマートフォンのカメラ機能の向上により、フィルム写真の需要は急激に縮小しました。「もう誰もフィルムなんて使いません」という状況に陥り、コダックは2012年に経営破綻するという悲劇的な結末を迎えました。
最も皮肉なのは、デジタルカメラの基本技術を1975年に世界で初めて開発したのはコダックだったという事実です。しかし、当時の経営陣は「デジタルカメラはフィルム事業を脅かす」という懸念から、この革新的技術を積極的に展開することを躊躇しました。「我々はフィルム会社である」という自己認識が強すぎたのです。

「我々はフィルム会社だ」という自己認識が強すぎたために…結末は悲劇そのものだった
(Photo:sylv1rob1 / Shutterstock.com)
その後もデジタル技術への投資は続けましたが、常に「フィルム事業を守る」という前提があり、思い切った事業転換ができませんでした。過去の成功体験から抜け出せず、フィルム事業に代わる新たな収益の柱を確立できないまま、時代の波に飲み込まれてしまったのです。
かたや大胆に変貌した富士フイルム、明暗を分けたのは
一方、同じくフィルム会社だった富士フイルムは、まったく異なる道を選びました。1990年代後半、富士フイルムの古森重隆CEO(当時)はデジタル化の波を早期に察知し、「フィルム市場は必ず縮小する」という厳しい現実を社内に突きつけました。そして2000年に「第二の創業」と位置づける大胆な事業転換を宣言したのです。
富士フイルムの変革の特徴は、古森CEOの強烈な危機感とアスピレーションをベースとした強力なリーダーシップのもと、フィルム製造で培った技術を徹底的に分析し、それらを活かせる新分野を戦略的に開拓した点にあります。たとえば、フィルムのコラーゲン制御技術は化粧品「アスタリフト」シリーズに応用され、写真の画像処理技術は医療診断機器に、フィルムの精密塗布技術は液晶ディスプレイの偏光板保護フィルムの製造に活かされました。さらに積極的なM&Aにより医薬品分野にも進出し、医療ヘルスケア、高機能材料、ドキュメントソリューションを新たな収益の柱として確立しました。
この結果、2023年度の富士フイルムの連結売上高は2兆3,680億円、営業利益は2,262億円に達し、かつてのフィルム会社は総合ヘルスケアカンパニーへと生まれ変わりました。写真関連の売上比率は全体の約10%にまで縮小していますが、会社全体としては過去最高の業績を更新し続けています。
この両社の明暗を分けたのは、変化に対する姿勢の違いです。コダックが過去の成功にしがみつき、自社のアイデンティティを「フィルム会社」と固定的に捉えていたのに対し、富士フイルムは「技術を持った会社」と自己を再定義し、その技術を活かせる新たな市場を積極的に開拓したのです。
柳井さんが「大企業病」を恐れる理由は、まさにこのコダックの事例に見られるような、過去の成功体験への執着が変革の妨げになることを熟知しているからです。だからこそ、ユニクロでは「常に組織を揺さぶり続ける」ことを重視し、過去の成功モデルに安住することなく、時代の変化に合わせて常に自己変革を続ける企業文化を醸成しているのです。「CHANGE OR DIE」というメッセージには、コダックのような運命を避けるための強い決意が込められていると言えるでしょう。
柳井さんは、組織が大きくなることで、中の人間にこのまま好業績が続くと錯覚する人が増えてくることも危惧しています。この対策として、ユニクロでは細部へのこだわりを重視しています。魂は細部に宿ります。小さいことを大事にしないと組織のカルチャーはどんどんルーズになります。ですから、あいさつやコミュニケーションの質から、責任の所在、投資判断の精度、経費管理まで、徹底して点検し続けています。
ユニクロの社長を務める塚越大介氏は「当たり前のことを徹底的に積み重ねる」という柳井さんの言葉を引用し、「凡事徹底」の重要性を強調しています。「我々はテックカンパニーではないので、毎日一店舗一店舗、商品一枚一枚の積み上げがグループ全体の売上になる」と述べており、「凡事徹底」ができなければ売上高5兆円、10兆円という将来の目標達成も難しいと考えています。
また、デジタル変革を「CEOアジェンダ」と明確に位置づけ、会社の未来を決する最重要経営課題として取り組んでいます。これは単なるIT化ではなく、社内カルチャー、ビジネスモデル、組織、人事など多方面の変革を包含するものであり、大企業病を防ぐための重要な取り組みの1つとなっています。
業績評価の割合は「利益変化50%/育成責任50%」
大企業病を避けるもう1つの重要な取り組みが、「各部門での教育の徹底」です。組織が大きくなるにつれて、新しく入ってくる人材や既存の社員に対する教育の質と量が低下すると、組織全体の能力も低下していきます。これを防ぐために、ユニクロでは各部門での教育に力を入れています。
特に注目すべきは、各部門を担当している執行役員自らが、責任を持って教育を行う仕組みです。一般的な企業では、社員教育は人事部の役割とされ、執行役員はほとんど教育には携わりませんが、ユニクロでは異なります。各部門が行動指針となる原理原則をつくって、実践していけるような教育の体系を構築しています。教育の資料も部門ごとに作ります。執行役員が責任者・リーダーになって、人を育てるという仕組みが徹底されているのです。
執行役員ともなれば、忙しくて教育どころではないのではと思われるかもしれませんが、柳井さんは教育こそがリーダーの仕事だと考えています。
私がユニクロ在籍中にユニクロの執行役員が教育に使う時間を調べたところ、通常は業務時間全体の5%程度、多くても10%程度でした。一方、柳井さん自身は30%を使っていて、できることならば50%は使いたいと言っていたほどです。そこで柳井さんとすり合わせ、執行役員の業績評価の割合を「利益変化50%/育成責任50%」にするという大胆な変革を行い、人材育成・後継者育成のドライブを図りました。
各部門の教育プログラムは非常に体系的です。まず、「業務の流れがどうなっているか」を明確にし、「それぞれに求められているスキル」を整理して、各キャリアステージで「こういうことができるようにならないといけない」と目標を設定します。
そして「今どこまでできているのか、できていないのか」を診断し、できていない部分を強化します。
「余計なことをしてくれた」の声もあったが…
この「部門別教育」がなぜ重要かと言うと、専門知識やスキルはFRMICや人事部が開く研修では細かく教えられないからです。それぞれの部門でその部門のエキスパートが系統立てて教える必要があるのです。
もちろん、ひと昔前は違いました。特に中途入社組は「お手並み拝見」といった感じで、系統立てられた教育は用意されていませんでした。そのため、OJTでユニクロ流の仕事を覚えなければいけない状況でした。
優秀な人が多いので、それで組織にフィットする場合もありますが、結果として、本当は能力がありながらも、組織に馴染めず、会社を去る人も一定数いたのが現実です。組織として人材を十分に活用できない「もったいないこと」が起きていました。
こうした事態を改善するため、「各部門を担当している執行役員が責任を持って人を育てよう」という方針が打ち出されました。私がユニクロでFRMIC担当役員だったころの取り組みです。当然、執行役員には大きな負荷がかかることなので、「余計なことをしてくれた」と悪者になりましたが、後に「やってよかった」と言われました。

『ユニクロの戦略』をクリックすると購入ページに移動します このような教育の徹底は、「チャレンジし続けさえすれば誰でも成長できる」という信念に基づいています。そして、ユニクロでは単に言葉だけでなく、実際にチャレンジを促す仕組みをいくつも構築しています。
たとえば、従業員1人ひとりの自己実現をサポートするため、従業員が自身のキャリアゴールを設定し、上司とともに「個別育成計画」を作成・実行する制度を導入しています。また、年2回の目標管理制度(MBO)を通じて、上司からのフィードバックだけでなく、同僚や他部署からの多面的評価も取り入れ、仕事に対する気づきや学びを促しています。
各部門での教育を徹底することで、組織全体の能力を高め、環境の変化に対応できる強い組織を維持しています。